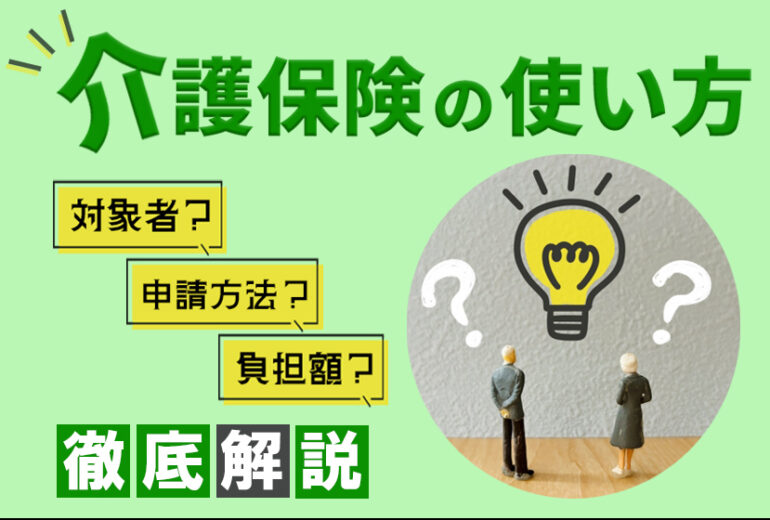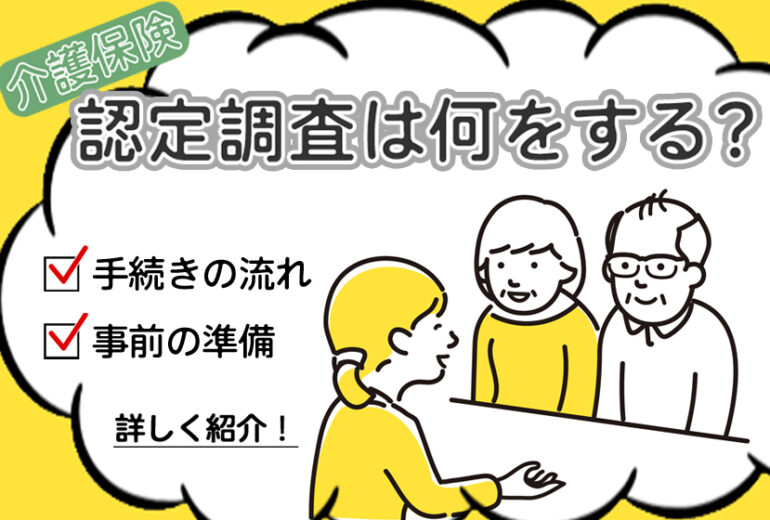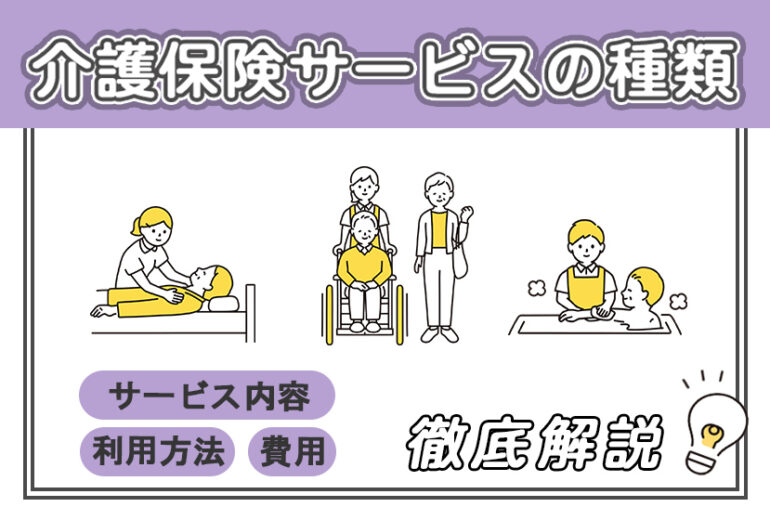冬は、ヒートショックや感染症などのリスクが高まる季節です。高齢になると、身体機能や免疫機能の低下により体調を崩しやすく、健康状態に気を配って過ごす必要があります。当記事で解説するのは、寒い季節の高齢者に起こりやすいリスクとその対策です。高齢者が寒い季節を健康に過ごすため、できることから始めましょう。
1 高齢者が冬に注意すべき7つのリスク

寒い時期は、外気温の低さや乾燥により、体調を崩す高齢者が増加します。ここからは、高齢者が気を付けたい冬のリスクを7つ紹介します。
1-1 ヒートショック
ヒートショックとは、急な温度変化により血圧が激しく上下し、体に負担がかかることで起こります。症状は、めまいや失神であり、脳血管疾患・心筋梗塞といった脳や心臓の疾患につながる場合もあります。浴室では、ヒートショックによって濡れた床で転倒したり、浴槽で溺れたりするリスクもあるため、十分に注意しましょう。
高齢者は、血管の老化により血圧が変動しやすく、ヒートショックのリスクが高くなります。長湯や水分をとっていないときも血流に負担がかかり、ヒートショックを起こしやすい状態です。ヒートショック対策には、温度差の解消や水分補給が有効だと言われています。予防のため、10度以上の温度差がある場所ではヒーターを設置する、入浴の前後に水を飲むなど、日頃の心がけが大切です。
なお、冬のヒートショック予防には全館空調付の住宅もおすすめです。全館空調について詳しくは下記のページで紹介しているため、ぜひご参照ください。
1-2 感染症
感染症のウイルスは低温と乾燥を好みます。冬場はウイルスが繁殖・拡散しやすく、感染症が流行するため、マスク・手洗い・うがいといった基本的な対策が重要です。冬に流行がみられる感染症として、インフルエンザ・ノロウイルス・溶連菌感染症・マイコプラズマ肺炎などがあります。以下で、高齢者が特に気を付けたい感染症のインフルエンザとノロウイルスを紹介します。
- インフルエンザ
インフルエンザは、12~3月頃に流行のピークをむかえる感染症です。症状は、高熱・頭痛・関節痛などで、重症化すると気管支炎や肺炎のリスクがあり、高齢者にとって命の危険をともないます。
インフルエンザの感染経路は、感染者の咳やくしゃみなどで感染する「飛沫感染」が多い傾向です。感染を防ぐには、外出時のマスク、帰宅時の手洗い・うがい、室内の加湿などが効果的です。また、インフルエンザワクチンの接種も、重症化を防ぐ効果があると言われています。高齢者は自治体などからワクチン接種の助成を受けられるので、必要に応じて活用しましょう。
- ノロウイルス
ノロウイルスは二枚貝に含まれているケースが多く、冬場に流行する食中毒の原因になります。ノロウイルス感染症の症状は、嘔吐・腹痛・下痢・発熱などで、1~2日程度続きます。高齢者は嘔吐や下痢による脱水症状が起こりやすく、重篤化しやすい傾向です。
ノロウイルスは感染力が強く、ウイルスが付着した食物を食べたり、感染者の嘔吐物・便に触れたりして感染する場合も少なくありません。感染症予防には、手洗いや加熱調理、次亜塩素酸ナトリウムを用いた消毒に効果がみとめられます。
1-3 低体温症
低体温症は、寒い場所でゆっくりと身体機能が低下し、意識障害やけいれんなどが起こることです。低体温症の予防には、暖かい場所で過ごすことや、体を保温することが大切です。
高齢者の場合、寒さを感じにくい、体温を調節する機能が低下しているといった理由で、低体温症のリスクが高くなります。室内での低体温症を防ぐためには、室温18度以上・湿度40%以上に保つよう調整しましょう。なお、低体温症は、筋肉量の少ない人や、低栄養の人ほど気を付けなければなりません。日頃から、栄養バランスの整った食事をとり、運動を習慣にすると、低体温症予防につながります。
1-4 冬の脱水症
冬の脱水症は、夏場と異なる原因で起こるため、注意が必要です。冬は空気が乾燥する一方で、気温が低く喉が渇きにくいという特徴があります。高齢者は特に、喉の渇きを感じにくく、水分摂取量が低下しやすい傾向です。脱水症は血流が滞るので、血圧が急激に変化しやすく、ヒートショックを引き起こすリスクもあります。冬場は喉が渇いていなくても、定期的に水やお茶を飲むなど、水分の接種を心がけましょう。
1-5 低温やけど
低温やけどは、約50度以下のものに長時間触れることで生じます。湯たんぽ・カイロ・電気毛布など、冬場によく利用する防寒グッズは、低温やけどの原因の1つです。高齢者は肌が弱いことや、感覚機能の低下により、気付かないうちに低温やけどが起こっているケースがあります。
低温やけどを防ぐには、熱源を直接肌にあてないこと、長時間の利用を避けることが大切です。具体的な予防策には、湯たんぽをタオルやカバーで包む、カイロは衣類の上から貼る、就寝時には電気毛布を切るといった方法があります。
1-6 窒息
正月に食べる機会の多い餅は、喉に詰まらせて窒息しやすい食べ物です。高齢者の場合、嚥下能力の低下や唾液量の減少によって、窒息のリスクが大きくなります。厚生労働省のデータによれば、65歳以上の餅による窒息事故は、全体の半数以上が年末年始に起こっています。
餅を食べるときは、サイコロ程度の大きさに切って、水分と一緒に食べることを意識しましょう。万が一を考え、家族が窒息のサインや背部叩打法を学んでおくのも、事故防止に有効です。
(参考:政府広報オンライン「餅による窒息に要注意!喉に詰まったときの応急手当は?」)
1-7 体力や身体機能の低下
冬は、寒さや感染症の影響で外出を控える高齢者も多くいます。家に引きこもりがちになると、体力や身体機能が低下し、体調を崩しやすくなります。寒い季節には、近所を散歩する、室内でできる体操にチャレンジするなど、体を動かすよう心がけましょう。運動が習慣になると、関節痛の緩和やうつの予防にも役立ちます。
また、冬場の乾燥による皮膚トラブルも高齢者に多くみられます。老人性乾皮症は、加齢により皮膚の水分保持能力が低下した状態です。老人性乾皮症によって皮膚に痒み・薄い亀裂・白い粉のようなものが出る場合もあります。乾燥を防ぐためには、肌をこすらないことや、保湿剤の使用が効果的です。
2 高齢者が冬を健康に過ごすための6つのポイント

冬の健康リスクは、ちょっとした心がけや日頃の習慣で対策できます。ここから紹介するのは、高齢者が寒い時期を健康に乗り切るためのポイントです。
2-1 部屋や外との温度差を小さくする
屋外と室内や、部屋と部屋の温度差を小さくすると、ヒートショックの予防になります。特に、室内の温度・湿度に気を配ると、低体温症や感染症のリスク予防にも効果を発揮します。
ヒートショックは温度差が10度以上あると起こりやすいため、廊下・トイレ・浴室に暖房器具を設置するのがおすすめです。暖房器具には、センサー式や防水仕様、薄型のものなどさまざまな種類があるので、使いやすいものを選びましょう。
また、風呂に入るときは浴室に湯をかけて温まる、外出時には防寒グッズで保温するなど、日頃のちょっとした心がけでヒートショックや低体温症を予防できます。
2-2 マスク・手洗い・うがいなど感染症対策
マスク・手洗い・うがいといった基本的な感染症対策は、冬を健康に過ごすために大切です。マスクは飛沫感染を防ぐほか、ウイルスが付着した手が、手や口に直接触れるのを防ぎます。家族の中に感染者がいるときは、感染者も非感染者の家族もマスクを付けたほうが予防効果が高まります。
手洗いは、石けんやソープを使い、15~30秒程度かけて丁寧に行いましょう。手拭きにタオルを使用している場合は、1日1回は交換すると菌の繁殖を防げます。
2-3 水分を意識的にとる
水分摂取は、ヒートショックや冬の脱水予防になります。水分は、必要量以上を一気にとると尿として体外に排出されるので、約200~250mlをこまめに補給したほうが効果的です。水分をとるタイミングは、食事中・起床後・体を動かす前後・15時のおやつ・入浴の前後・就寝前など、時間を決めるのがおすすめです。嚥下機能に不安がある高齢者の場合、ゼリー飲料やとろみのついたスープなら、安心して飲み込めます。
2-4 体を適度に動かす
運動は、身体機能の低下を防ぎ、筋力や免疫力アップが期待できます。高齢者は、1日10分程度の体操・1日20分程度の散歩・1週間に2回程度の筋トレ・1週間に3回程度の軽いスポーツのいずれか1つ以上を行うことが推奨されています。寒い時期は、室内のラジオ体操や、座ってできる体操などでも構いません。運動が習慣になると、心身ともに健康な状態に近付きます。
(参考:厚生労働省「身体活動・運動」)
2-5 食事は喉に詰まらせにくい調理法を選ぶ
高齢者は、嚥下機能の低下や唾液量の減少により、誤嚥・窒息を起こしやすい状態です。誤嚥とは、咀嚼して飲んだ食べ物が気管に入ることです。高齢者の場合、吐き出す機能も低下しているので、気管に入った食べ物から細菌感染が起こり、誤嚥性肺炎にかかるリスクがあります。
餅をはじめとした窒息を起こしやすい食べ物は避けるか、小さく切りましょう。普段の食事でも飲み込みにくい、むせるといった症状があるなら、かかりつけ医に相談の上、介護食を取り入れるのも方法の1つです。食事を楽にするには、飲み物をゼリー飲料にしたり、汁物にとろみを付けたりすると、無理なく飲み込めるケースもあります。
2-6 身近な人とのコミュニケーションや見守りサービスの活用
寒い時期は家にこもることが多く、友人や近隣の人とのコミュニケーションが減少傾向です。冬に発生しやすい高齢者のヒートショックや低体温症などは、発見が遅れると命にかかわります。万が一のときにすぐ対処できるよう、周囲の人の協力や、見守り体制を整えることも大切です。高齢者の見守りは、介護サービスによる訪問・警備会社の見守りシステムの導入・配食サービスの利用など、さまざまな方法があります。見守りサービスの導入を考える際は、高齢者や家族の状況に合わせ、地域で利用できるものを確認しましょう。
3 高齢者の冬の健康&安全チェックリスト

冬のトラブルを防いで健康に過ごすには、生活習慣を整え、心身の異変にすぐ気付くことが大切です。以下のチェックリストで、高齢者の日常生活の様子や、心身の状況について確認できます。
生活習慣
|
心身の状況
|
生活環境
|
高齢者は感覚器官が鈍くなっている場合があり、自分でも気付かないうちに症状が悪化しているケースがあります。高齢者の冬のリスク対策のため、チェックリストを役立てましょう。
まとめ
高齢者が冬を健康に乗り切るためには、以下の6つがポイントです。
- 部屋や外との温度差を小さくする
- マスク・手洗い・うがいなど感染症対策
- 水分を意識的にとる
- 体を適度に動かす
- 食事は喉に詰まらせにくい調理法を選ぶ
- 身近な人とのコミュニケーションや見守りサービスの活用
冬のヒートショックや感染症などは、日頃の生活習慣とちょっとした工夫で予防できます。規則正しい生活や、室温の調整、水分接種を心がけ、家族みんなで元気に冬を乗り切りましょう。
高齢の親が健康を害すると、相続トラブルや家族間の不和に発展するケースも少なくありません。家族みんなが元気なうちから相続の準備を進めておくと将来も安心です。