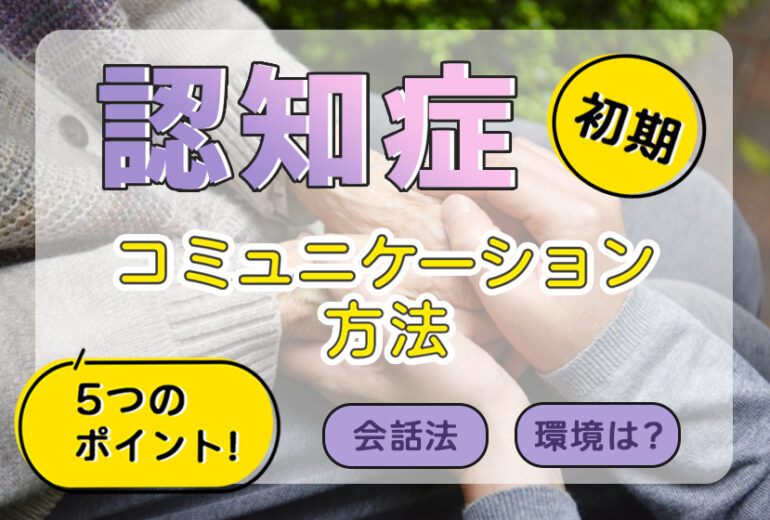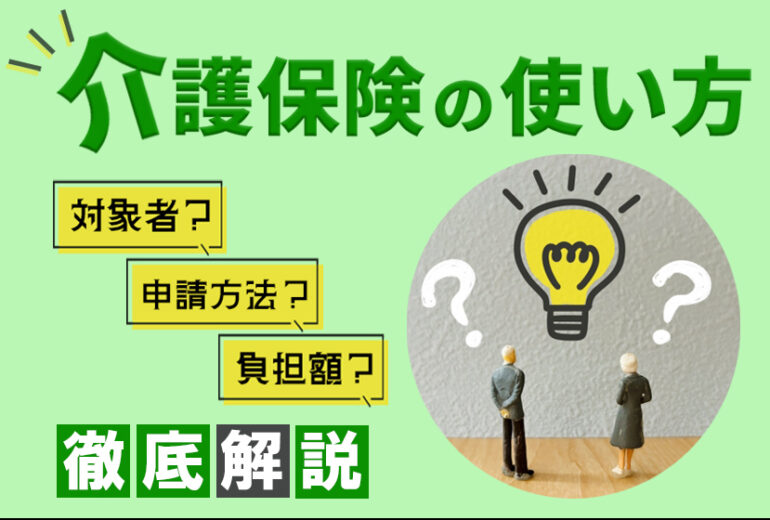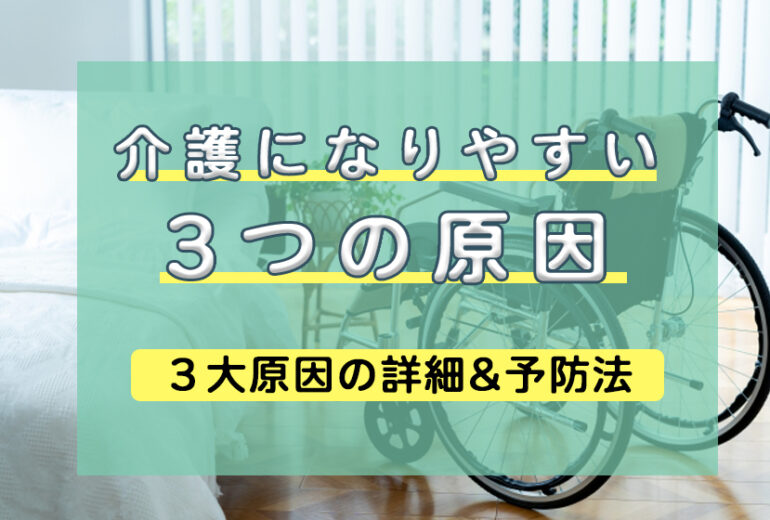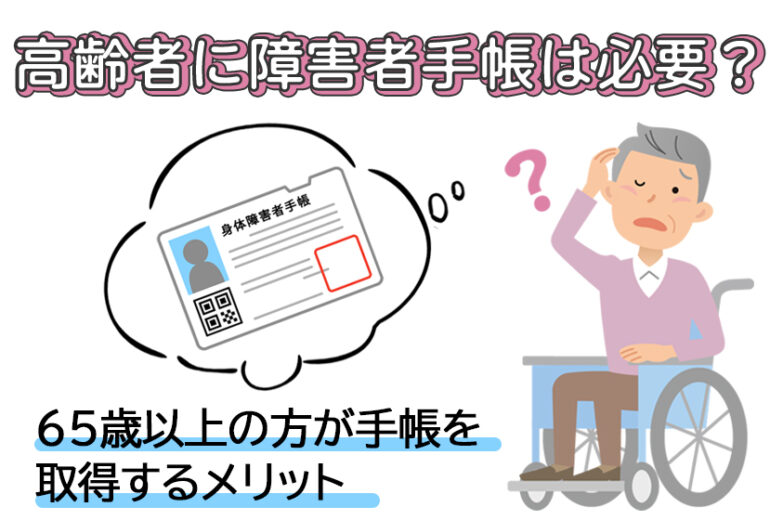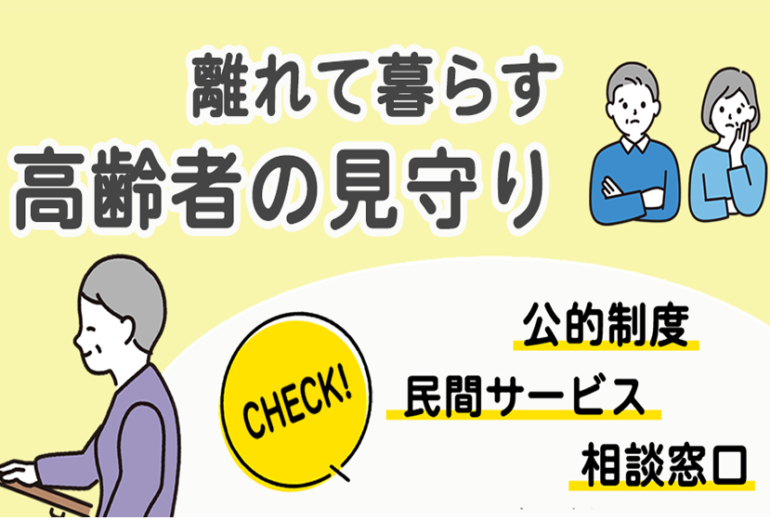親や身近な高齢者の介護に備えたいとき、何から行えばよいか不安に思う方がほとんどです。ヘルパーさんやデイサービスなどの介護サービスを使いたいときは、介護保険を利用するのが一般的です。
当記事では、介護保険サービスの種類・利用方法・費用といった事柄を詳しく紹介します。介護サービスをこれから利用したい方や、サービスの見直しをしたい場合の参考にしましょう。
1 介護保険サービスとは?

介護保険サービスは、要介護認定を受けて要介護・要支援に認定された人が利用できます。ここから紹介するのは、介護保険サービスの基本的な内容です。介護保険を知り、サービスの種類や内容について理解を深めましょう。
1-1 要介護認定が必要
介護保険サービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定を受けたい場合、自治体の介護保険担当窓口に申請します。身近な高齢者が要介護状態に該当するかわからない場合、地域包括支援センターに相談するのがおすすめです。
要介護認定を申請し、調査が行われると、自立(非該当)・要支援1~2・要介護1~5のいずれかの認定結果が通知されます。
| ・自立(非該当) 高齢者の日常生活に介護を必要とせず、自立した状態です。 自立の場合、介護保険サービスは利用できません。 ・要支援 要支援1~2に認定された方は、介護予防サービスが利用可能です。 介護予防サービスには、訪問看護や通所リハビリ、ショートステイなどがあります。 ・要介護 要介護1~5に認定された方は、介護サービスが利用できます。 介護サービスには、ホームヘルプやデイサービス、ショートステイなど多くの種類があります。 |
在宅で介護保険サービスを利用するためには、まずケアプランを作成します。ケアプランは、どのようなサービスをどれくらい利用するか、高齢者一人ひとりの状態に合わせたサービス計画です。
ケアプランの作成について、要支援の方は地域包括支援センターの職員、要介護の方は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当します。施設で介護サービスを利用したいときは、入居希望の施設に直接連絡を取りましょう。
1-2 サービスは居宅・施設・地域密着型の3種類
介護保険サービスを大別すると、居宅・施設・地域密着型の3種類があります。
居宅サービスは、自宅などに住みながら利用する介護サービスです。
施設サービスは、施設に入所し、介護やリハビリを行うサービスです。
地域密着型サービスとは、地域の特色に合わせて提供される小規模のサービスをいいます。
1-3 費用負担のしくみは?
介護保険サービスを利用したときは、利用料の1割を自己負担します。残りの9割は、公費と介護保険料から支払われる仕組みです。例えば、1,000円のサービスを利用した場合、自己負担は100円です。ただし、一定以上の所得がある高齢者の場合、自己負担は2~3割になります。
なお、介護保険で利用できるサービスには限度額が設定されています。限度額は、要介護度によって異なり、要介護度が重いほどたくさんサービス利用が可能です。例えば、要介護1の限度額は167,650円、要介護3の限度額は270,480円なので、要介護3のほうが支給限度額が多くなります。1か月のサービス利用が限度額を超えたときは、超えた分の費用を全額自己負担します。
2 在宅で利用できるサービス

居宅サービスは、利用者の状態や生活環境にあわせて多くの種類があるため、必要なサービスを組み合わせて利用することになります。以下で紹介するのは、在宅の方がよく利用するサービスです。
2-1 ケアプラン作成
ケアプランとは、介護サービスの利用計画書です。ケアプラン作成は、多くの場合ケアマネジャーが担当します。ケアマネジャーは、施設や居宅介護支援事業所に所属し、本人や家族の希望を取り入れたケアプランを作成します。
一方で、ケアプランは本人や家族が自分で作ることも可能です。自分でケアプランを作る場合、書類手続き・情報収集・事業所間の連絡調整・毎月の自治体への報告といった手続きを個人で行う必要があります。ケアプラン作成は、専門家であるケアマネジャーに任せるのがおすすめです。
2-2 訪問サービス
訪問サービスは、介護スタッフや看護師が自宅に来てサービスを提供します。訪問サービスの種類には、訪問介護・訪問看護・訪問入浴・訪問リハビリ・居宅療養管理指導などがあります。
・訪問介護
訪問介護は、訪問介護員(ホームヘルパー)が来て、食事・排泄・入浴の手伝いや、掃除・洗濯・調理といった家事を行います。訪問介護は、高齢者本人の介護・介助を行うサービスであり、家族への援助はできません。
・訪問看護
訪問看護は、看護師が自宅で行う医療ケア・栄養管理・療養上の世話・終末期ケアなどのサービスです。看護師は、医師の指示に基づいて医療ケアや療養上の世話を実施します。
・訪問入浴
訪問入浴は、看護師と介護スタッフが自宅に来てサービスを提供します。訪問入浴のやり方は、スタッフが簡易浴槽を持ち込み、看護師1人・介護士2人の3人体制で入浴をサポートするのが一般的です。
・訪問リハビリ
訪問リハビリは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などのリハビリ専門職が自宅に来て、日常生活の維持向上や自立を目指したリハビリを行います。
・居宅療養管理指導
居宅療養管理指導は、通院が困難な利用者の自宅に、医師・歯科医師・看護師・管理栄養士・薬剤師などが来て、療養や健康管理のアドバイスを行うサービスです。
2-3 通所サービス
通所サービスは、利用者が日中に施設へ通い、食事提供、入浴介助、レクリエーション、リハビリなどを行います。通所サービスの送迎は施設が担当し、利用者宅を順番に回るのが一般的です。通所サービスには、通所介護(デイサービス)や通所リハビリがあります。
2-4 宿泊サービス
宿泊サービスはショートステイと呼ばれ、短期入所生活介護と短期入所療養介護の2種類があります。ショートステイのサービス内容は、特別養護老人ホームなどに短期間入所し、生活上の世話や機能訓練を受けることがメインです。在宅介護の家族負担を軽減したいときや、一時的に家で介護できないとき、ショートステイを利用できます。
2-5 福祉用具レンタル
車いす・介護ベッド・スロープなど、13品目の福祉用具は、介護保険でレンタルできます。また、排泄にかかわる用品や衛生面に配慮が必要な用品はレンタルがなじまないため、介護保険で購入できます。
なお、福祉用具の中にはレンタル可能な要介護度が決まっているものもあるため、自身の介護度が該当するか利用前に確認しましょう。例えば介護ベッドをレンタルしたいとき、要支援と要介護1の方は介護保険貸与の対象外です。
2-6 住宅改修
介護保険を利用し、手すりの取り付け・段差解消・移動円滑化のための床材変更・引き戸への取り換えといった改修が可能です。介護保険の住宅改修は、生涯に20万円が限度額です。例えば1割負担の方が20万円の改修を行った場合、18万円が償還払いされます。ただし、転居した場合や要介護度が3つ以上重くなったときは、再び住宅改修の支給対象になります。
3 施設を利用できるサービス

介護保険の施設サービスは、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院の3つです。上記3つは公的施設であり、費用が抑えられるなどのメリットがあります。なお、有料老人ホームやサ高住の中にも「特定施設入居者生活介護」と呼ばれる介護保険の指定を受けた施設があります。ここからは紹介するのは、介護保険の施設サービスについて各施設の違いや入居条件です。
3-1 介護老人福祉施設
介護老人福祉施設は特養とも呼ばれる施設で、食事・入浴・排泄といった日常生活の介護や、機能訓練、健康管理などを行います。入居は原則要介護3以上の方で、寝たきりや認知症の方も受け入れ可能です。施設は、スタッフの目が届きやすい従来型、個別性を重視したユニット型などのタイプがあり、終身利用できます。
3-2 介護老人保健施設(老健)
老健は、要介護1以上の方が在宅復帰を目指して一時的に入居する施設です。老健では、日常生活の介護のほか、リハビリテーションを行います。入居期間は高齢者によって異なりますが、概ね3~6か月での退所を目指しています。老健を利用するタイミングは、退院して自宅に戻るまでの期間や、特養などの入居待機中が多い傾向です。
3-3 介護医療院
介護医療院は、医療ニーズの高い要介護1以上の方が入居する施設です。介護医療院では、日常生活の世話に加え長期的な医療ケアが可能であり、看取りにも対応しています。医療設備が充実している介護医療院ならば、喀痰や褥そうケアなど日頃の医療ケアが必要な高齢者や、終末期ケアのニーズを持つ方も受け入れ可能です。
3-4 特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護は、指定を受けた有料老人ホーム・軽費老人ホーム・サ高住などで利用できるサービスです。特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設を特定施設と呼びます。特定施設では、介護保険サービスを施設内で受けられます。一方、住宅型有料老人ホームといった特定施設以外の施設で介護保険サービスを利用したい場合は、外部の事業者と契約することになります。
4 地域密着型サービス

地域密着型サービスは、地域の実情に応じてサービスが展開されており、その自治体に住民票のある人だけが利用できます。以下で紹介するのは、地域密着型サービスの一例です。地域密着型サービスは、自治体によって提供されるサービスが異なるので、詳細はお住まいの地域でご確認ください。
4-1 認知症高齢者が利用できるサービス
地域密着型サービスの1つに認知症の方が入れるグループホームがあります。グループホームは、9人以下の認知症高齢者が介護スタッフの支援を受けながら生活します。認知症の方でも自立した生活が送れるよう、高齢者自身が家事などの役割を持っていることがグループホームの特徴です。なお、グループホームに入居できるのは、要支援2か要介護1以上の方です。
4-2 通いや泊まりを組み合わせたサービス
地域密着型サービスのうち小規模多機能型居宅介護は、訪問・通所・ショートステイを同じ事業所から提供します。訪問や通所は通常、1週間に何回など頻度を決めて提供されます。小規模多機能型居宅介護の場合、利用者の希望に応じて訪問・通所・ショートステイを組み合わせ利用可能です。
4-3 小規模な老人ホーム
地域密着型サービスの1つに、定員29人以下の小規模な老人ホームがあります。小規模な老人ホームに入居するメリットは、家庭的な雰囲気で生活できることです。また、地域密着型サービスはその地域に居住する人のみが対象になるので、住み慣れた地域に住み続けられることもメリットです。近所にある老人ホームならば、家族や知人が訪問しやすいでしょう。
4-4 夜間や緊急時の訪問
夜間対応型訪問介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、夜間と緊急の訪問介護・看護を行うサービスです。夜の介護は、介護者の睡眠不足や、疲労・ストレスの蓄積につながり、在宅介護をきつく感じる要因になります。夜間に訪問介護・看護を利用できれば、家族の負担が軽くなるでしょう。
まとめ
介護サービスを利用するときは、介護認定を受け、介護保険でサービス利用すると経済的な負担が軽くなります。また、介護保険を利用すると相談できる場所が明確になり、精神的な負担も軽減されます。介護保険サービスの利用を検討している人は、地域包括支援センターに相談するのがおすすめです。また、たくさんの介護サービスの中から何を利用すればよいか迷ったときは、ケアマネジャーなどの専門職に相談しましょう。
介護が始まっても、高齢者本人や家族がいきいきと過ごせるよう、介護サービスをご活用ください。