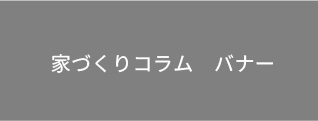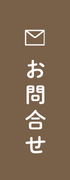子育てをする上で、赤ちゃんのかけがえのない一瞬を残していきたい…
そう考えるママ、パパも多いのではないでしょうか。
今回の記事では、
・赤ちゃんの写真はいつ撮る?
・赤ちゃんの写真を自分で撮るときに、これだけは知っておきたい知識
・赤ちゃんの写真を自分で撮るコツ
・赤ちゃんの写真を自分で撮るならおすすめフォト
などについて解説します。
赤ちゃんやお子さんの写真をたくさん撮っていきたい、と考えている方はぜひ最後までご覧ください。
赤ちゃんの写真はいつ撮る?

ここでは、赤ちゃんの写真はいつ撮るべきか、について解説します。
基本は日常生活の中での写真もおすすめですが、何かしらのイベントのときの撮影もぜひおすすめしたいです。
具体的には以下の通りです。
・ニューボーンフォト
・お宮参り
・お食い初め(百日祝)
・ハーフバースデー
・初節句
・月齢フォト
・1歳バースデー
それぞれを詳しく見ていきましょう。
・ニューボーンフォト
生後0~28日までの赤ちゃんを新生児と呼びますが、その時期の赤ちゃんの写真をニューボーンフォトと言います。
たった28日間しかない新生児の頃の写真は、ぜひ残しておきたいところです。
生まれて間もない新生児の赤ちゃんの記念写真は独特な雰囲気があり、この時期にしかない姿を形に残しておくことができます。
・お宮参り
お宮参りとは、赤ちゃんが無事に産まれたことをその土地の守り神に報告し、これからの成長を願い神社に参拝する行事です。
赤ちゃんにとってはこれが人生で初めての神社参拝になります。
スタジオ撮影では、「一つ身」と呼ばれる着物と一緒に犬張り子、金封、でんでん太鼓などの縁起物をつけて撮影します。
撮影目安は生後1ヶ月前後ですが、ご家族の都合や赤ちゃんの体調をみて、撮影時期を検討していただければいいでしょう。
・お食い初め(百日祝)
お食い初め(百日祝)は生後100日目に行う行事で、赤ちゃんの健やかな成長と今後食べるものに困らないようになどの意味を込めて祝い膳を食べさせる真似をします。
最近ではレストランやホテルで祝い膳を用意していただける場所も多いので、気軽に行う事ができるようになってきました。
スタジオ撮影でも祝い膳と一緒に撮ったり、赤ちゃんの食べさせる真似をしながら撮ったりできるところもあります。
他にも赤ちゃん用の着ぐるみなどもあります。
この時期になると赤ちゃんの表情もかなり豊かになってくるので色んな表情や仕草を撮ることができるでしょう。
・ハーフバースデー
ハーフバースデーは、日本では生後6ケ月目を祝う行事として定着しています。
この頃の赤ちゃんはちょうど一人で座れるようになったり、ずりばいを始める時期です。
今まで仰向けだった赤ちゃんの行動範囲が少しずつ大きくなってコミュニケーションもよく取れるようになってきます。
スタジオ撮影では赤ちゃんの動きが出てくるので、今まで以上にいろんなポーズで撮影することができるでしょう。
うつ伏せしたり、座ったり、物を持ったり。また、本格的にハイハイを始める前なので、まだ手足がむちむちです。
裸んぼ撮影が一番可愛いのも、このハーフバースデーの時期でしょう。
・初節句
初節句とは赤ちゃんが生まれてから最初に迎える「節句」の日のことです。
男の子は5月5日端午の節句、女の子は3月3日桃の節句の日にそれぞれ兜やお雛様を飾り祝います。
初節句は赤ちゃんが生まれた月によって生後何カ月目で迎えるか様々です。
スタジオ撮影では兜やお雛様と一緒に撮ることが多いです。
また、ご自宅でも道具を自分で準備して撮影することもできます。
上記で書いたようにお子さまの誕生月によって生後何か月目で迎えるか様々なので、生後3ヵ月以内など早くに初節句を迎える場合は一年先送りして翌年に初節句として撮影される方も多いです。
・月齢フォト
1歳になるまでの1年で、赤ちゃんは驚くほどどんどん成長していきます。
産まれてから1年の間に寝返りができるようになりお座りができるようになったり…と驚くほど日々の成長が目に見えて分かるのがこの時期です。
子どもの成長ぶりはどんな瞬間もこの目に焼き付けておきたいですが、記憶はどうしても薄れていきます。
そんな時におすすめなのが、赤ちゃんの成長を想い出としておしゃれに写真に残せる「月齢フォト」なんです。
近年はもはや定番化してきている「月齢フォト」。
月齢フォトでは、毎月産まれた日と同じ日にちを記念日として、毎月1枚ずつ写真を撮っていきます。
ママは毎日忙しくて大変かもしれませんが、月齢フォトは後に大切な宝物になるので、ぜひ時間を作って撮ってみてはいかがでしょうか。
・1歳バースデー
毎年迎えるお誕生日の中でも特別なのが、生まれてから初めて迎えるお誕生日です。
ここまで無事に成長できた喜びをぜひお祝いしましょう!
地域によっては「選びとり」や「一升餅」などで赤ちゃんの今後の成長を祝うこともあります。
スタジオ撮影ではドレスやタキシードを借りて着て華やかに撮ったり、可愛い着ぐるみを着てキュートに撮ったり様々なバリエーションでの撮影が楽しめるでしょう。
お子さまによっては人見知りも始まってスタジオに慣れるのに時間がかかることもあるので、お気に入りのおもちゃや、お菓子などを用意しておくと安心です。
赤ちゃんの写真を自分で撮るときに、これだけは知っておきたい知識

ここでは、赤ちゃんの写真を自分で撮るときに、これだけは知っておきたい知識を解説します。
主に、カメラ(一眼レフ、ミラーレス一眼レフ)の下記の項目について解説します。
・レンズの種類
・絞り(F値)
・シャッタースピード
・ISO感度
それぞれを詳しく見ていきましょう。
・レンズの種類
一眼レフカメラやミラーレス一眼カメラでは様々なレンズを用いて撮影します。
カメラのレンズには主に以下の種類があります。
・広角レンズ
・望遠レンズ
・単焦点レンズ
<広角レンズ>
広角レンズは名の通り、広い範囲を写すことに長けています。
そのため、広大な景色を写す際や屋内を写す際には広々と写す際に活用されることが多く、風景写真では定番の存在です。
<望遠レンズ>
望遠レンズは、特定の被写体をクローズアップするようなシーンで活用できるレンズで、一眼カメラだからこそ撮影できるジャンルの一つです。
乗り物や動物、スポーツ撮影においては、望遠レンズが特に活用できるジャンルで、望遠レンズの使用率のが高くなるほどです。
特殊なレンズジャンルであることから、使うシーンや注意点も特殊であるため、慣れるまで少し時間のかかるレンズジャンルでもあります。
<単焦点レンズ>
ズームレンズとは異なり、レンズ側で画角の調整を行うことができないのが単焦点レンズです。
画角が固定されることで、写真に変化を加えたい場合は、自分自身が動きながら調整する必要のある難しさがあります。
しかし、単焦点レンズを使った撮影は、制約があるからこそ、考えながら撮影することで写真が上達する手段でもあります。
また、ズームレンズよりも明るさを特徴としたレンズが多く、ボケを活かした撮影がしやすいです。
赤ちゃんの撮影をするなら、赤ちゃんに近づいて撮影できる単焦点レンズがおすすめです。
・絞り値(F値)
絞り値はF値とも呼ばれ、レンズから入る光の量を表す数値を指します。
F値は焦点距離をレンズ口径で割ることで計算されます。
F値 = 焦点距離 ÷ レンズ口径
F値が小さいとレンズから入る光の量が多くなります。
また、ピントの合う範囲(被写界深度)が浅くなるため、被写体の前後がボケやすくなります。
一方、F値が大きいとレンズから入る光の量が少なくなり、写真は暗くなります。
また、F値を大きくする(絞り込む)ことで被写界深度が深くなり、被写体の前後のピントが合う範囲が広くなります。
・シャッタースピード
カメラは、シャッターボタンを押した時だけ、奥にあるセンサーに光が当たり、その瞬間が写真として残る仕組みです。
そして、写真を適切な明るさにするために、センサーに光を当てる時間を調整する仕組みがあります。
それは、「1/1000秒(0.001秒)」という目にも止まらない時間から、「1秒」といった少し長めの時間まで、状況によって変わってきます。
この時間を、「シャッタースピード」と呼んでいます。
シャッタースピードは、文字通りシャッターの速度を指し、1/60、1/125、1/250などと記され、シャッターを開く時間(秒数)を表します。
例えば、「1/60」は、「1/60秒間シャッターを開いてセンサーに光を取り込む」という意味です。
分母の数字が大きいほどシャッターの速度が速く、よりブレのない写真が撮れます。
・ISO感度
カメラではISO感度という「光に対する敏感さ」を数字で設定することができます。
この数字を高く設定することで暗い場所でも明るく撮影することができます。
つまりISO感度を上げればシャッタースピードを速くすることも可能です。
ただし、ISO感度を上げすぎるとノイズ(ざらつき)が気になる場合もあるので注意しましょう。
ここまで、赤ちゃんの写真を自分で撮るときにこれだけは知っておきたい知識を解説しましたが、難しくてカメラの設定が分からない…という方もいらっしゃると思います。
そんなときは、「オートモード」で撮影するのもおすすめです。
オートモードは、撮影状況や撮影シーンから、絞りやシャッタースピード、ISO感度、ホワイトバランスなどをカメラが自動で設定し、撮影する機能です。
カメラまかせで撮影するため、初心者でも使いやすいモードといえます。
赤ちゃんの写真を自分で撮るコツ

ここでは、赤ちゃんの写真を自分で撮るコツについて解説します。
お手持ちのスマホやカメラでもできますので、ぜひやってみてください。
具体的には以下の通りです。
・自然光は必須
・背景や床、壁は白がおすすめ
・露出を駆使
・カメラの高さ
・連写する
・小道具の準備
・赤ちゃんの目を見ながらたくさん声をかけよう
それぞれを詳しく見ていきましょう。
・自然光は必須
自然な表情をきれいに撮るなら、フラッシュなどではなく自然光が一番です。
室内をしっかり明るくしてあげます。
レースカーテン1枚にし、柔らかい光を部屋に取り込むことで、ブレや暗さを防ぎましょう。
1歳未満の赤ちゃんは一日のほとんどを室内で過ごすため、室内写真が多くなると思われます。
室内の撮影でよくある失敗は、窓をバックにしたことで、逆光で顔が暗くなってしまう事です。
明るい窓際で撮影する際は、後述する露出のテクニックを使いましょう。
また、自然光を反射するレフ版を準備するのも一つの手です。
・背景や床、壁は白がおすすめ
主役の赤ちゃんをしっかりクローズアップするには、背景がごちゃごちゃしていてはいけません。
白や明るい色のシーツやおくるみを広げたり、白い壁を利用して背景をシンプルにすると、ふんわりした感じの写真が撮れ、主役を引き立たせることができます。
あまり背景に工夫ができない状況の時は、できる限り背景が写らない様に赤ちゃんに寄って撮ったり、写る部分だけ物を退けるなどしてみましょう。
・露出を駆使
赤ちゃんのお肌は、その名の通り少し赤く見えます。
透き通るような肌感を表現するには、少し明るめに露出補正をしましょう。
赤ちゃんの場合、肌だけでなく、服も白系や淡い色のピンクやブルーなどが多いですが、そういった明るい色の服を着ていると、カメラのオートモードでは、全体的に明るいと判断して、少し暗めに撮影しようとする傾向があります。
そこで、予め露出補正を1/2から2/3程度+側に設定しておくことで、服装の白っぽさや肌の透明感を表現することが可能です。
撮影された画面を見ながら、お好みの明るさに調整しましょう。
・カメラの高さ
赤ちゃんを主役に撮影するときには、赤ちゃんの可愛さだけに夢中にならず、背景の状態にも注目しましょう。
見下ろすようにばかり撮っていると、背景がいつもベッドのシーツなどあまり変わらない状態になってしまいます。
そこで、カメラを赤ちゃんの目線と同じ高さに構えてみましょう。
すると、背景にお部屋の雰囲気が写ったり、赤ちゃんの見ている風景が感じられる写真になりますよ。
特にうつ伏せやお座りしている赤ちゃんの写真を撮る場合は、カメラの高さを合わせることは重要なポイントです。
・連写する
赤ちゃんを撮影するときは、基本的に連写するのがポイントです。
なぜならば、赤ちゃんは大人が望むように止まってポーズをとったりしてくれないからです。
いつどんな動きをするのか分からないからこそ、連写して赤ちゃんの可愛い姿を見逃さないようにしましょう。
・小道具の準備
生後3ヶ月を過ぎた辺りから、赤ちゃんにおもちゃなどを持たせると、徐々に握れる様になってきます。
初めてのおもちゃや、お気に入りの人形などと一緒に撮ると可愛さが倍増します。
毎年お気に入りのオモチャと写真を撮ることで、成長を比較し楽しむこともできますよ。
また、お祝いにもらった品と一緒に撮るのもいいですね。
・赤ちゃんの目を見ながらたくさん声をかけよう
赤ちゃんを撮るときに、液晶画面やカメラの覗き窓をずっと見ながら、赤ちゃんがいい表情になるのを待っていませんか?
プロのモデルさんならまだしも、赤ちゃんはカメラのレンズを見て笑顔になるという意識を持っていませんし、ありません。
そんな時は、大まかに写す範囲を決めたら、カメラから目を離して、赤ちゃんに直接目を向けてみましょう。
赤ちゃんはカメラのレンズよりも、人の目や顔を見たほうがいい表情をしてくれます。
特にその人が大好きなママやパパだったら、嬉しい表情が出やすいです。
カメラの画面は赤ちゃんが画面から外れてないか確認する程度にして、赤ちゃんと直接表情や言葉でコミュニケーションを撮りながらシャッターを押してみましょう。
今までよりもずっと生き生きした表情の写真が撮れているはずです。
赤ちゃんの写真を自分で撮るならおすすめフォト

ここでは、赤ちゃんの写真を自分で撮るならぜひ撮ってほしいおすすめフォトを紹介します。
具体的には以下の通りです。
・笑顔
・泣き顔
・うつ伏せ
・お座り
・つかまり立ち
・パーツフォト
それぞれを詳しく見ていきましょう。
・笑顔
赤ちゃんは、新生児の頃はあまり目が見えていませんが、生後3ヶ月くらいになると、だんだんと目が見えるようになってきます。
まだ近い距離で、ぼやっとしか見えていないときでもママやパパの顔をなんとなく認識していて、目で追うようなことも増えてきます。
人の顔をマネするといった特徴もあるので、至近距離でママやパパが満面の笑顔で話しかけてあげる事で赤ちゃんは笑いやすくなります。
・泣き顔
意外に思われるかもしれませんが、実は泣き顔もおすすめです。
笑顔ももちろん可愛いですが、泣き顔もそのときしか見れない表情をしているので、ぜひ一枚撮っておくことをおすすめします。
あとから写真を見返したときに、「あのときは大きな声でいっぱい泣いていたなぁ…」など、思い出して懐かしく思えるはずです。
・うつ伏せ
赤ちゃんのよって個人差はありますが、生後およそ3ヵ月ほどで首が座ってきます。
うつ伏せにするとより長い時間、力強く首を持ち上げられることもあります。
今までずっと仰向けだった赤ちゃんがうつ伏せしている姿はとっても新鮮で感動的な場面です。
中にはうつ伏せの方が機嫌がいい!というようなたくましい子もいます。
写真を撮る時はシャッターをすぐ切れるようにあらかじめカメラを準備したうえで、赤ちゃんをうつ伏せさせるようにしましょう。
シャッターチャンスは一瞬です!
ただし、うつ伏せができるようになったばかりの赤ちゃんは、まだまだ不安定で赤ちゃんに負担もかかるので、あまり無理はさせないように注意しましょう。
・お座り
お座りができるようになる時期には大きな個人差があることが分かっています。
生後7~8ヶ月で約7割の子どもがお座りができるようになるとされていますが、生後4~5ヶ月で0.5%、生後6~7ヶ月約3割の子どもがお座りができるようになるとの報告もあります。
意外に思われるかもしれませんがお座りしている写真も大切な1枚になります。
当たり前に座っている姿を見るともはやそれが普通に見えてくるものですが、これも立派な成長の証です。
ちょこんと座っている姿も赤ちゃんだとなぜか可愛くみえてしまうもの。
好きな衣装を着せたお座りフォトは、とても可愛い写真になるでしょう。
また、兄弟姉妹でお座りして撮る2ショットも可愛いですよ。
ただ、腰がすわってきたとはいえ、自分で完璧にお座りできるのはもう少し先のこと。
この時期は何かに寄りかかったり、バンボ(補助イス)を使ったりすることで写真に変化をつけることができます。
・つかまり立ち
赤ちゃんがつかまり立ちをするようになるのは、個人差はありますが生後10ヶ月頃と言われています。
いきなり何かにつかまって立ち上がるというわけではなく、まずはずりばいの状態から手足をついて身体を浮かせる高ばいやお尻を高く浮かせたハイハイなどを行った上で、徐々につかまり立ちができるようになります。
つかまり立ちをしながらこちらを見る赤ちゃんは、想像しただけでも可愛いですよね。
何かにつかまって上にあるものに手を伸ばしてみたり、つたって移動してみたり、おぼつかない姿はとても可愛らしいものです。
ただ、つかまり立ちをはじめたばかりの赤ちゃんは、すぐに転んでしまう可能性があるので安全には十分に注意しなければなりません。
撮影を行う際は、赤ちゃんの転倒に気を付けながら行いましょう。
・パーツフォト
赤ちゃんパーツフォトとは、赤ちゃんの手足や顔などをパーツごとに写した写真のことです。
かわいい赤ちゃんの小さな手足や、赤ちゃん特有の表情をアップにして写真に残します。
生後間もない赤ちゃんは成長著しいですが、パーツフォト撮影をすることでかわいい姿を細かいところまで記録できます。
パーツフォトは、赤ちゃんの撮影にとてもおすすめです。
その理由は、生まれたばかりの赤ちゃんの小さな手足や表情がその時だけの特別なものだからです。
また、赤ちゃんは寝ている時間が多いため、パーツフォトをゆっくり撮影できるという点もあげられます。
自然なポーズのまま、かわいいパーツフォトの撮影をしましょう。
<パーツフォトにおすすめの部位>
・顔全体
・目、鼻、耳などの細かい部位
・手
・足
<パーツフォトを撮る時のコツ>
・顔全体を撮る時に意識したいポイントは目にピントを合わせることです。さらに、赤ちゃんの瞳に光を写り込ませるようにすると、表情が活き活きとした感じになり、素敵になります。
・赤ちゃんの手や足のパーツフォトを撮るときは、光の入り方に気をつけましょう。被写体の後ろや斜め後ろから光が入るようにすることで、逆光を利用した優しい雰囲気の写真が撮れます。
<家族も参加するパーツフォトの撮り方>
赤ちゃんパーツフォトの撮影には、ぜひご家族のみなさまも参加してください。
「ママの指をにぎる赤ちゃんの手」、「お兄ちゃんの足と赤ちゃんの足」など、大きさ比べのように撮影することで、赤ちゃんの小ささが際立ったかわいい写真が撮れます。
<パーツフォトを作るメリット>
パーツフォトを作るメリットとして、以下のことが挙げられます。
・「その時だけの特別な」小さな手足や表情を残せる
・全身だけでなく体のパーツを意識して撮影できる
・寄り(アップ)で撮ると成長過程を細かく把握できる
・両親・兄弟姉妹と似ている箇所が発見しやすい
パーツフォトと月齢フォトを組み合わせて写真を撮っていくと、赤ちゃんの成長の過程を写真に記録することができます。
撮影は、起きているときはもちろん、むしろ寝ているときがシャッターチャンス!ありのままの自然な姿をカメラに収めましょう。
まとめ

今回は赤ちゃんやお子さんの写真をたくさん撮っていきたい、と考えている方向けに赤ちゃんの写真を撮るタイミングやコツなどを解説しましたが、いかがでしたか?
お祝い行事の数だけ撮れる写真も異なります。
赤ちゃんが生まれてからは毎日が本当に慌ただしく過ぎていくと思います。
忙しい毎日の中、気づいたら大事な記念日を過ぎていた!なんてことにならないようにしっかりそれぞれの時期を確認して計画的に撮影をしていきましょう。
また、あくまでも主役は赤ちゃんです。
赤ちゃんが撮影に疲れてしまわないよう、赤ちゃんの様子を見ながら撮影を進めてください。
この記事がこれから我が子の写真を自分でたくさん撮っていきたい、と考えている方の参考になれば幸いです。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。