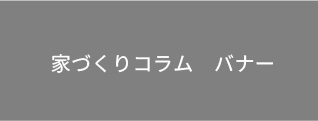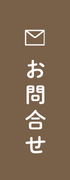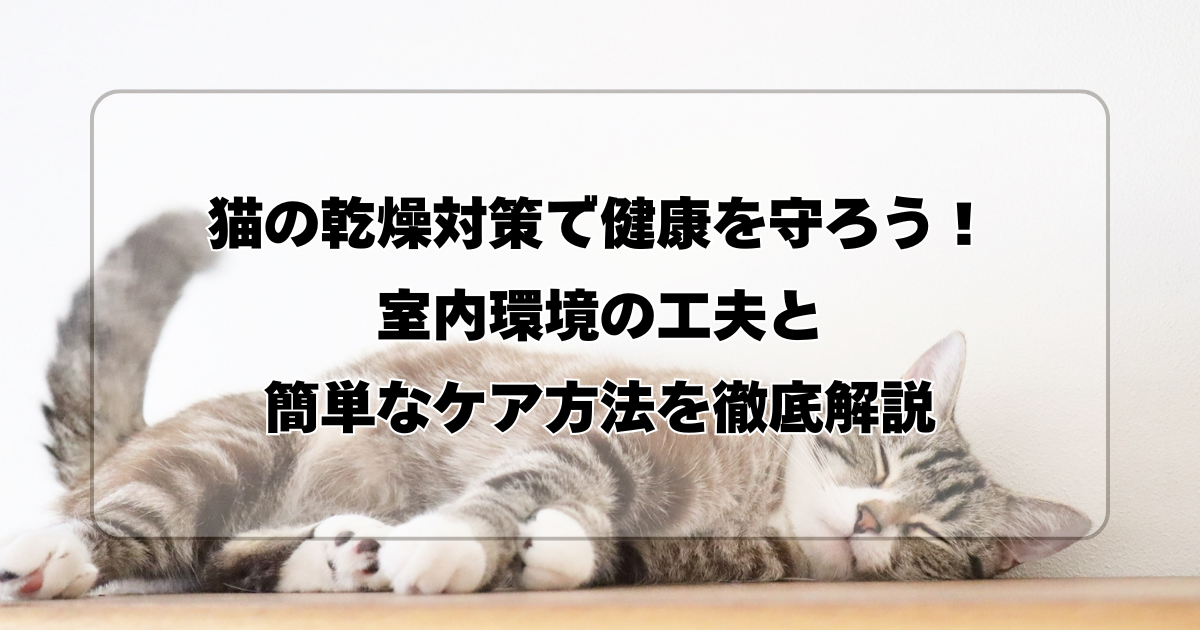
冬場や暖房を使用する時期は、猫にとって乾燥が大きなリスクになることをご存知ですか?乾燥は、猫の肌荒れや毛並みの乱れ、静電気、さらには呼吸器系のトラブルを引き起こす原因となる場合もあります。とくに子猫やシニア猫は影響を受けやすく、注意が必要です。この記事では、猫の健康を守るための乾燥対策について詳しく解説します。室内環境の工夫や日々のケア方法を取り入れて、大切な愛猫と快適な冬を過ごしましょう。
冬に部屋の空気が乾燥するのはなぜ?

冬に空気が乾燥する理由の1つは、気温が低くなると空気中の水分が水滴や氷になり減ってしまうためです。また、暖房の使用も乾燥を助長する原因となります。エアコンや電気ヒーターは加湿機能がないと空気をさらに乾燥させてしまうので注意しましょう。
とくにエアコンは、部屋の温度を上げると湿度を下げてしまう性質の暖房器具です。エアコンの風が直接体に当たると、肌や髪がさらに乾燥しやすくなります。猫だけでなく、人間にとっても避けたい環境です。
さらに、最近の住宅事情も影響しています。気密性や断熱性の高い家が増えたおかげで、部屋の温度が一定に保たれるようになりました。一方で、気温が高いと空気中の水分量が少なくなり、乾燥を感じやすくなってしまいます。冬の部屋はとくに乾燥しやすい環境になっているので、愛猫との暮らしを快適にするためにも乾燥対策を必ず行いましょう。
猫の肌が乾燥しているサイン

猫は言葉で「肌がかゆい」と伝えられないので、飼い主さんが気づいてあげる必要があります。猫が乾燥肌になったときに見られるサインを紹介しますので、小さなサインも見逃さないようにしましょう。
フケが増える
猫の肌は、約21日ごとに新しい肌に生まれ変わります。乾燥肌になるとサイクルが乱れてしまい、古い皮膚だけでなく正常な皮膚も一緒に剥がれてしまう原因です。多くのフケが出てくるだけでなく、サイズが大きかったり脂っぽかったりという特徴があります。フケの量がいつもより多い、または見た目に異変がある場合は、愛猫が乾燥肌になっているかもしれません。
肉球がひび割れる
猫の乾燥肌は皮膚だけでなく、肉球にも影響が出ます。肉球は足の裏にあり、乾燥を気にしなくても大丈夫な印象を持っている飼い主さんも多いでしょう。しかし、乾燥がひどくなると肉球がひび割れてしまいい、歩くたびに痛みを感じる可能性もあります。床に直接触れる部分なので、定期的な肉球の状態チェックが重要です。少しでも乾燥している様子が見られたら、早めに保湿してあげます。
毛づくろいした身体がベタベタしている
空気の乾燥によって注意したいのは肌だけでなく、口の中の水分不足です。通常であれば、自分で毛づくろいをするとサラサラになります。しかし、口の中が乾燥した状態で毛づくろいをすると、唾液が濃くなって被毛がベタベタしてしまうのです。口の中が乾いていても、においがなければ問題ありません。ただし、口臭を感じるようであれば、口内炎がないかチェックしてみましょう。
とくに乾燥の影響を受けやすい猫の特徴

猫によって乾燥の影響を受ける度合いは異なるものの、シニア猫や短毛種、被毛がないスフィンクスのような猫は乾燥の影響を受けやすいとされています。愛猫が乾燥に弱い場合は、日頃から特別な配慮とケアが必要です。
シニア猫
年齢を重ねた猫は、皮膚や被毛の保湿機能が低下しています。そのため、乾燥の影響を受けやすいだけでなく、免疫力も弱くなっているのが一般的です。乾燥による健康リスクが高いので、成猫よりも慎重な対応が求められます。
短毛種の猫
被毛が短い猫は、長毛種の猫に比べて皮膚が外気にさらされやすいというのが特徴です。以下のような猫種は、乾燥によるダメージを直接受けやすい傾向があります。
| ・スコティッシュフォールド ・マンチカン ・ベンガル ・アメリカンショートヘア ・ロシアンブルー |
肌が露出している猫
被毛がほとんどないスフィンクスなどの猫は、乾燥の影響を最も受けやすい種類です。皮膚そのものが空気に触れてしまうため、肌荒れや乾燥肌のリスクが上がります。飼い主さんによる日常的なケアが重要となり、乾燥しない環境づくりも重要です。
飼い主さんが今すぐできる猫の乾燥対策

寒い季節になると、人間だけでなく猫にも乾燥対策が必要となります。愛猫の肌にかゆみや炎症が起きたり、皮膚がカサカサになってフケが出たりしないよう、飼い主さんは注意しましょう。愛猫の健康を守るために今すぐできる乾燥対策を3つ紹介します。
部屋を加湿
空気が乾燥していることがトラブルの原因となるため、加湿器を使って部屋の湿度を上げましょう。部屋の湿度は50~60%を目安にし、40%以下だと要注意です。また、60%を超えてしまうとダニやカビが発生しやすくなってしまうため、適切な湿度を保つよう心がけます。
適切な水分補給
猫はもともと水をあまり飲まない傾向があるものの、暖房が効いた部屋では乾燥防止のためにも十分な水分補給が必要です。水分を取ると皮膚や被毛の健康を保つだけでなく、腎臓病や下部尿路の病気の予防につながります。水をあまり飲まない猫には、ウェットフードを与えるのも効果的です。
こまめな保湿ケア
乾燥する季節は、猫の肉球や皮膚も乾燥しやすくなります。ペット用の保湿クリームを使って、こまめにケアしてあげましょう。皮膚が乾燥すると、フケが出たり、かゆみで頻繁に体を舐めるようになります。さまざまな皮膚トラブルを引き起こす可能性があるだけでなく、細菌感染のリスクも高まる点に注意が必要です。
猫と暮らす家におすすめの加湿器4選と選び方のポイント

乾燥対策としておすすめの加湿器ですが、使用時にミストが気になって猫が落ち着かない、加湿器を倒してトラブルが発生してしまうという問題があります。加湿器を選ぶ際は、デザインだけでなく性能も考慮することが大切です。
気化式加湿器
気化式加湿器は、水を吸ったフィルターに風を当てて水分を蒸発させる仕組みとなっています。シンプルな構造で、濡れたタオルを振り回して乾かす状態をイメージするとわかりやすいかもしれません。熱や蒸気が発生しないため、猫との暮らしでも安全に使用できます。
最近では、和紙に水を吸わせて自然に蒸発させるタイプや、素焼きの陶器に水を入れるだけの加湿器も人気です。見た目が可愛く、電気代が安いのでコストパフォーマンスにも優れています。一方、気化式加湿器のデメリットは、加湿力が弱く、広い部屋では乾燥を十分に防げない点です。
気化式加湿器は次のような人におすすめします。
| ・電気代を節約したい人 ・他の加湿器と一緒に使いたい人 ・家電の音が気になる人(ファン付きのタイプは音が出る場合もある) ・ミストが出ないタイプを使いたい人 |
スチーム式(加熱式)加湿器
スチーム式加湿器は水を加熱して沸騰させ、やかんのように蒸気を出すタイプの加湿器です。昔から使われている方式で、加湿力は非常に高くなっています。加熱することで雑菌が繁殖しにくいため、衛生面で安心して使えるのが特徴です。
一方、白い蒸気が出るため、猫が興味を持ちやすく、いたずらされる場合もあります。加熱部分が熱くなり、好奇心旺盛な猫は火傷に注意が必要です。ほかの加湿器と比較して、電気代が高いというデメリットもあります。
スチーム式加湿器は、以下のような人におすすめです。
| ・とにかく保湿したい人 ・愛猫がミストや動作音を気にしない ・衛生面が気になる人 |
超音波式
超音波式加湿器は、デザインが豊富でおしゃれなものが多く、価格も手頃なタイプが多くなっています。超音波で水を細かい粒子にして噴出する仕組みで、音が静かで電気代は安いのも特徴です。
ただし、水をそのまま霧状にして噴き出すため、加湿器内で増えた雑菌やカビ、水中の塩素がそのまま室内に拡散されてしまいます。周囲が湿りやすく、水中のミネラル分が白い塊になって家具や家電に付着するケースも少なくありません。猫が濡れた床を舐めてしまうと、雑菌やカビを取り込んでしまうリスクにも注意が必要です。
超音波式は猫との相性が良いとは言えないものの、以下のような人におすすめします。
| ・デザインや価格を重視する人 ・頻繁に加湿器を丁寧に掃除できる人 ・愛猫の入らない部屋で加湿器を使いたい人 |
ハイブリッド式(加熱気化式)
ハイブリッド式加湿器は、気化式にヒーターを組み合わせたタイプです。部屋の湿度に合わせて加湿方法を自動で切り替えてくれるのが特徴で、湿度が低いときはフィルターに温風を当てて素早く加湿し、湿度が安定すると通常の気化式に切り替わります。そのため、スチーム式のように電気代が高くなりすぎないというのがメリットです。
ハイブリッド式は、気化式の弱点である加湿力の低さを補う効率の良さから人気が高まっています。ただし、高性能な分、本体価格が高めで、機種によっては動作音が大きいというのがデメリットです。加熱気化式以外にも、超音波式にヒーター機能を加えた「加熱超音波式」もハイブリッド加湿器として販売されています。
ハイブリッド式加湿器は、以下のような人におすすめです。
| ・初期費用がかかっても高性能な加湿器が欲しい人 ・安全性を重視したい人 ・愛猫が大きな動作音を気にしない性格 |
冬の乾燥対策とあわせて暖房設備について知りたい方は、下記の記事をお読みください。
猫は冬に暖房が必要?最適な設定温度と寒さ対策で健康を守る家づくりのポイント!
加湿器のアロマ機能は安全性に注意が必要
アロマディフューザーとして使える加湿器は人気があるものの、エッセンシャルオイルの中には猫に有害な成分が含まれている場合もあります。たとえば、虫除けに使われる「ティートゥリー」の精油は、猫が嗅ぐと中毒を起こすと注意喚起されています。エッセンシャルオイルは植物から抽出された濃縮成分で、解毒能力が低い猫には適していません。猫とアロマの関係は不明な点も多いため、使用に関しては安全性に十分配慮しましょう。
乾燥に強い家づくりのポイント

今すぐできる猫の乾燥対策についてお伝えしましたが、今後マイホーム購入の予定がある方は家づくりの段階で以下のような工夫をするのがおすすめです。また、信頼できる住宅販売会社であれば、「猫との暮らし」にフィットしたプランを提案してもらえます。打ち合わせの段階で、気軽に相談してみましょう。
風通しを良くする
間取りをオープンにし、仕切りを少なくします。湿気がたまりやすい場所に扉を設けないことで、風通しの良い環境をつくるためです。加湿器で湿らせた空気を効率良く家中に運べ、湿度が高くなりすぎるのも防げます。
調湿効果のある素材を使用する
床や天井、壁に湿度を調整する効果の高いものを使うのもおすすめです。木材や漆喰(しっくい)、珪藻土は「調湿建材」と呼ばれ、部屋の湿度が高いときは湿気を吸い取って、湿度が低いときには湿気を放出して乾燥を防げます。
換気システムを充実させる
高気密高断熱住宅が乾燥しやすいのは、家の隙間が少なく、自然換気が起こりにくいためです。室内の空気循環が悪いため、24時間換気システムを上手に活用しましょう。空気の流れが良い家では、結露が生じにくいというメリットもあります。
猫の乾燥対策は加湿だけでなく、住まいの見直しも大切

愛猫の健康を守るためには、冬の季節は乾燥対策が欠かせません。とくに暖房使用時には室内が乾燥しやすく、肌荒れや呼吸器のトラブルを引き起こす可能性があります。部屋の加湿や適切な水分補給、保湿ケアなどを取り入れるのも効果的です。また、加湿器は、種類や安全性を考慮しながら選ぶ必要があります。将来的に家づくりを計画している場合はペットと暮らす住宅を扱う会社に相談するのがおすすめです。乾燥に強い住環境を整え、愛猫と過ごす寒い季節をより快適にしましょう。
猫と快適に暮らせる家づくりについては、以下の記事を参考にお読みください。